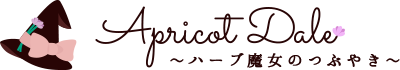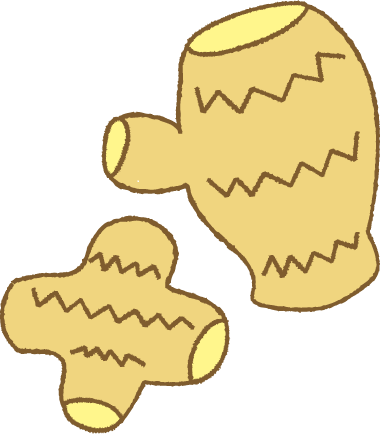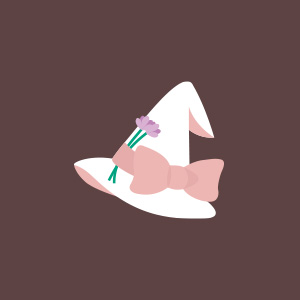しばしば耳にする質問です。
私個人の意見を言わせていただければ・・・
スパイスとハーブの間に明確な線引きはできないと思っています。
スパイスを日本語にすると「香辛料」。
つまり、香りや味に圧倒的な特徴があるということではなかろうか?
それに対してハーブは「薬草」または「香草」。
ハーブを香草と訳す場合は、スパイスと重なるところが多い。
しかしハーブの中には香りにあまり特徴を感じられないものもある。
また、香りに圧倒的な特徴があっても、香辛料に分類することのないものもある。
例えば「ジャーマンカモミール」。
精油成分が含まれているから香草といいたいところだが、
スパイスに分類する習慣性は見当たらない。
ジャーマンカモミールはれっきとした「ハーブ」だ。
では「シナモン」はどうだろう?
シナモンは香辛料でもあり、ハーブでもあるのではないだろうか?
フェンネルも両方の役割を果たしていると思える。
香りや味というのは、私たち生体にきっと何らかの作用をもたらすと思われる。
薬草とは薬になるような草のこと。「薬効のある」草のこと。
そういう意味ではスパイスは薬草のグループに入るのではないだろうか?
考えれば考えるほど、この2種の境界線はあいまいになってしまう。
かつて黄金に匹敵するほどの価値があるとされ、
その所有を巡って戦争まで起こしてしまったスパイス。
味気ない食事を続けていたヨーロッパの人々にとって、
スパイスは食文化を豊かにするとともに、
肉の保存料としても無くてはならないものになったのだとか。
ハーブとスパイスの区別については、その国の習慣性にもよるのかもしれない。
日本では「スパイスで体を癒す」とはあまり言わない。
しかし、広い世界のどこかでは、「病をスパイスで癒す」という表現をする国もあるのかも・・・?
私自身、ハーブとスパイスの使い分けを明確にしているというワケではないが、
「料理の香り付けや辛味などの味付けに利用するときは「スパイス」。
薬効を期待する目的で使用するときに「ハーブ」と言うことが多い。
また、
「ハーブ」はハーブティーなどのように主材料として利用することが多く、
「スパイス」は料理の副材料として利用することが多いのでは?
つまり、
スパイス = 食用
ハーブ = 薬用をはじめとして染料、香料、栽培、観賞用などなど
と、使用範囲で分けるとしっくりくる気がする。
皆さんはどう思いますか?
まぁ、私個人としては・・・・
「そんなもんどっちでもいいんじゃない?」
というのが”本心”ですが、
ハーブの講師をしている以上、そんないい加減なことは言えないので、
もったいぶって四の五の言っちゃってます。