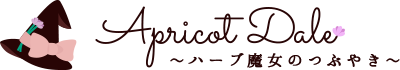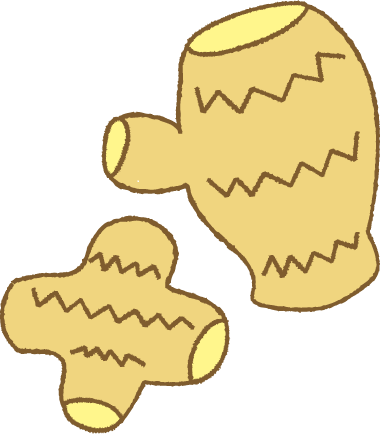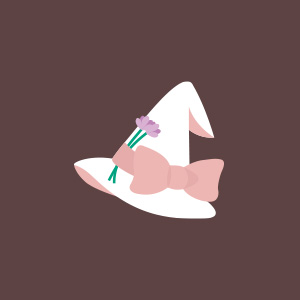今や高齢化社会真っ只中の日本。
1950年以降、
心身症や生活習慣病が日本人の健康を脅かしています。
それに伴い、
漢方薬の良さが見直され、
生薬類のニーズは高まる一方です。
それなのに・・・
日本での生薬自給率はな・な・なんと10%ちょい。
そして80%以上を中国からの輸入に頼っています。
高齢化社会は日本だけではありません。
中国も同じ。
中国国内でのニーズが高騰していることを理由に、
生薬の輸出制限を強めているため、
価格はうなぎのぼり。
今では生薬のことを
「第二のレアアース」と呼ぶまでになりました。
中国以外から輸入したくても、
その他のアジア諸国でも
伝統医学を重視し、
自国の生薬を守る姿勢をとり始めています。
伝統医学を重んじる発想転換の影には、
WHOの存在が大きいのですが、
そのWHOの栽培指針GACP
(薬用植物の栽培法、安全で清潔な環境での
栽培・収穫・調整加工などに関する指針)では、
野生植物の計画的採取地と保護について述べています。
日本に関係しているものとしては、
防巳(ボウイ)、黄柏(キハダ)、
厚朴(コウボク)、苦木(ニガキ)などです。
これらはどれもハーバルプラクティショナーの
植物化学科で使用した、
「薬学生のための天然物化学」に収載されている生薬です。
簡単に言うと、将来的には、
自国で使う生薬は、
責任を持って自国で栽培しなければならなくなるということです。
さて、そうなると、
日本でも薬用植物資源確保のための
種の保存と栽培技術の基盤固めが必要です。
かつて
人件費の高さと農村の高齢化を理由に
中国からの輸入に頼りきっていた日本がどれだけ頑張れるのだろう?
最近流行りの
工場内で栽培される野菜のように、
生薬ができないものだろうか?
現存している生薬がレアアースと呼ばれるならば、
そこに日本人お得意の
「機能性」を加味して、
機能性生薬なるものを開発すれば、
植物体として栽培する量を減らせるかも・・・
開発にお金はかかっても、
人件費が減らせるのでは?
そうなれば、
自給率100%どころか、
海外に輸出するのも夢じゃないかもねぇ。
とはいえ、
植物相手ではそう簡単にはコトは運ばないんだろうなぁ。
頭のイイ人頼みで恐縮ですが、
誰か、わたしの代わりに頑張って、
私の頭の中にある将来像を実現化してください。
とりあえず私は、
今までどおり、
自分の庭の薬草栽培に勤しみ続けます。